みなさん、FIREしたいですか?したいですよね?
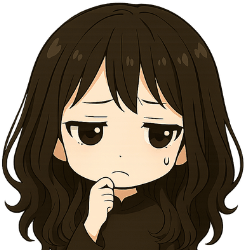
そりゃしたいですけど、教育、住宅、老後…人生のお金の悩みは尽きません
資産運用でNISAをされている方は多いと思いますが、iDeCoについては「資金が拘束される」「制度が複雑」といった理由から敬遠されがちです。実際の利用状況についても
- NISA口座は開設数2,647万口座(2025年3月末時点、日本証券業協会より)
- iDeCo加入者数は363万人(2025年3月末時点、iDeCo公式サイトより)
と、7倍以上の差があります。
しかし、実はNISAとiDeCoを併用することで、教育や住宅などの中期資金と老後資金を効率よく準備できることをご存じでしょうか?
敬遠されがちなiDeCoですが、NISAとの組み合わせを前提にすると多くの人におススメできる制度です。
この記事では、私が実際に資産形成を考える中で「なぜNISAとiDeCoの併用をオススメするのか」を解説していきます。

制度の概要やNISAだけでいい人などについても併せてご紹介します。目次をご用意していますので、気になるところからご覧ください。
NISAとiDeCoの違いについて
NISAは資産運用で得られた利益が非課税になる制度です。一方でiDeCoは掛金(拠出金)で資産運用するところは同じなのですが、掛金が所得控除の対象となり、運用益が実質的に非課税になるかは受取時に課税されるかどうかで決まります。
NISAは資産運用をするのであれば無条件でおススメできますが、iDeCoについては少しだけシミュレーションが必要です。
運用可能額と投資対象について
NISAの運用可能額(掛金の上限)は年間360万円、生涯累計で1,800万円です。
一方でiDeCoの運用可能額(拠出額の上限)は人によって異なります。上限はその方の状況によって異なるのですが、毎月5,000円以上1,000円単位で設定をします。なお、iDeCoにはNISAのような障害拠出金額の上限がありません。ここ、一つポイントです。
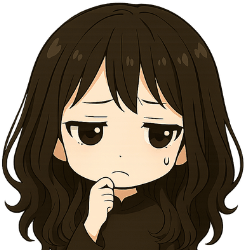
この拠出上限額の時点でややこしいんですよね…月額2万円、2万3千円、6万8千円のどれかになるのですが、詳しくはiDeCo公式サイトでご確認ください。
また、投資対象もそれぞれ決められたものから選ぶのですが、基本的には株式や債券などのリスク資産から選択するのですが、なんとiDeCoには定期預金もあります。
運用益非課税と所得控除の違い
NISAは資産運用で得られた利益が非課税になる制度です。キャピタルゲイン(買った時より高く売れた時の差額の利益)もインカムゲイン(配当や分配金などの利益)も国内の税金であれば非課税となります。人によって非課税の恩恵が変わることはありません。
iDeCoは掛金全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税の減額という形でメリットが得られます。その分受け取り時には元本も含めた全額が課税対象となってしまうのですが、受取時には「公的年金等控除」や「退職所得控除」が使えるため、条件次第ではほとんど課税されずに受け取れるケースもあります。
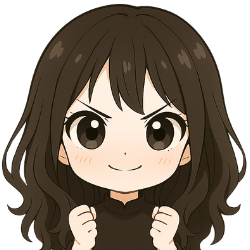
受取時に課税がされなければ、拠出時の所得控除の分だけiDeCoの方がオトクというわけですね!
iDeCoのメリットが大きな方は主に以下のような方です
- 収入の多い方(所得税の税率が高いので、所得控除の恩恵が大きい)
- 退職金制度のない方(一時金として受け取る際に、退職所得控除をフルに利用できる)
このように、使いようによってはNISAよりもメリットがあるとiDeCoですが、当然デメリットも存在します。
iDeCoが「不人気」と言われる理由
うすうすお気づきかもしれませんが、iDeCoはNISAに比べて制度が複雑で、「使いにくい」と感じられる点がいくつかあります。資金の流動性や制度の複雑さも敬遠される要因になっており、これらが「不人気」な原因じゃないかと思います。
iDeCoのデメリットについても整理してみます。
60歳まで資金を引き出せない
NISAとiDeCoを比較した際に誰もが思い浮かぶデメリットがこれだと思います。これについてはもう仕方がないというか、もともとが年金なのでそういうものと割り切るしかないです。
「老後資金」を「資産運用」で貯めたい人には関係ありませんが、「資産運用で増えたお金」を「老後資金にも充てたい」人には大きなデメリットです。要するに、老後資金だけを入れる貯金箱としてならiDeCoでよいのですが、人生で必要になるお金をがさっと入れる貯金箱としてはiDeCoは向いていません。

資産をどのように運用するかという点では比較対象となりますが、NISAの本質は余剰資金の運用、iDeCoの本質は老後への備えです。そのためこの2つを比較するのは違う用途のものを比較しているという考え方もあります。
受取時の税制を理解する必要がある
iDeCoは拠出した時点で所得控除という形でメリットを受けられますが、受け取り方によっては受取時に課税されてしまいます。
特に、一時金で受け取る場合は勤務先の退職金と退職所得控除を共有することになるため、退職金を多くもらえる方は課税時に不利になりがちです。
対策として、年金として受け取れば公的年金控除を使うことができます。
どちらかというと、この点では将来の税制改正が不透明だということが一番のデメリットなのかもしれません。
手数料がかかる
iDeCoはNISAと違い、利用に手数料がかかります。金額は取扱金融機関によっても違うのですが、最低でも月額171円、年額で2,052円が必要です。また、拠出を停止しても手数料が必要となります。
掛金が少ないと相対的に手数料の負担が重くなり、運用効率が下がってしまいます。
拠出額の設定が難しい
手数料とも関係しますが、拠出額の設定も悩ましいです。
NISAなら余裕資金の範囲で自由に積立額を増減できますが、iDeCoは一度設定すると原則として年単位でしか変更できず、柔軟性に欠けます。多くの人にとってNISAを年額360万円埋めることは難しいと思われますので、NISAにいくら、iDeCoにいくらと振り分けすることになると思いますが、この振り分けは…悩ましいですね。
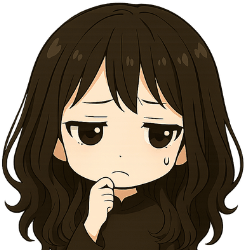
iDeCoはNISAと違って生涯上限枠もないので、使い切らなかった拠出額はそのまま消滅しちゃうんですよね。もったいない…これも悩みポイントです。
それでもiDeCoをオススメする理由
このように制度はやや複雑で資金の自由度も低いですが、うまく利用できれば得られるメリットは大きく、特にNISAと併用することで資産形成の幅をぐっと広げられるのです。
ここでは、iDeCoを積極的に利用すべき3つの理由をご紹介します。
NISAと組み合わせることでライフステージに応じた資金を準備できる
人生の資金需要を中期的なものと長期的なものに分けたとき、教育資金や住宅資金などの中期的なものをNISAで備え、老後資金などの長期的なものをiDeCoで備えるという住みわけができます。
メリットのところでもご紹介しましたが、受取時に全額非課税にすることができれば基本的にはiDeCoの方がNISAよりも節税効果は高いです。
この2つを併用することで、ライフステージごとに必要なお金を効率的に準備できます。

暴落時に取り崩さずに済むよう、現金比率も意識してみてください
所得控除で節税できたお金でNISAに投資ができる
iDeCoの掛金は全額が所得控除となり、その分だけ所得税や住民税の負担が軽くなります。
例えば所得税の税率が10%の方が月2万円(年間24万円)をiDeCoに積み立てると、年間で約5万円の節税効果が期待できます。
なお、ご自身がどの程度節税メリットがあるかという簡易シミュレーションがiDeCo公式サイトから行えます。
この「浮いたお金」をそのままNISAの積立に回せば、節税+資産運用のダブル効果を得られます。つまり、iDeCoを利用することで実質的に投資余力を増やし、NISAの活用にもつなげられるのです。
非課税での受取ハードルは実は高くない
これ、私が一番お伝えしたかったことです。iDeCoを一時金として受取る前提で「結局非課税にできるかわからない」という意見がありますが、だったら年金で受け取ればいいじゃない。
iDeCoを年金として受け取る場合、公的年金控除が使えます。65歳までは年60万円、65歳以上は年110万円が所得から控除されます。
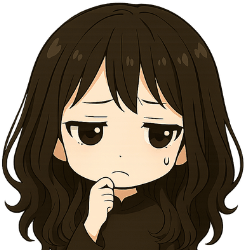
でも年間60万円、月5万円だとさすがに生活できないですよ…
そこでNISAですよ。例えば、月に15万円の収入が必要な場合、5万円をiDeCoから年金で給付を受け、10万円をNISAから取り崩すことで、月々の生活資金を確保しつつ、iDeCoも全額非課税で受け取ることができます。また、iDeCo以外に収入がなければ基礎控除も使えるので、非課税で受け取れる給付額はもっと増えます。
また、あまりに掛金が増えすぎた場合は公的年金(国民年金や厚生年金)の受給を繰り下げることでiDeCoの給付額が公的年金控除の額を超えないように調整もできます。
受け取り方さえ調節できるのであれば、iDeCoを非課税で受け取るのって、実はそんなにハードルが高くないと思います。
iDeCoが不要なケース(NISAだけで十分なケース)は?
ここまでiDeCoのメリットを解説してきましたが、すべての人にとって必ずしも必要というわけではありません。以下のような場合はiDeCoが不要、またはNISAを優先した方が良いでしょう。
- 毎月の生活資金に余裕がない場合(家計の見直しを優先)
- 収入が不安定な場合(スポット購入可能なNISAの方が好相性)
- 中期資金の蓄えが不十分な場合(運用するならNISAを優先。でも現金での備えも要検討)
- 所得税が非課税の場合(iDeCoの所得控除メリットがない。NISAを優先)
- 流動性を重視する場合(個人事業主やトレーダーなどで大きな資金需要が発生する場合)
- 絶対一時金で受け取りたいけど課税もされたくない場合
このように、ライフプランや資産状況によっては「NISAだけで十分」というケースもあります。大切なのは、制度を盲目的に使うことではなく、自分の将来設計に合った方法を選ぶことです。
まとめ:「NISA+iDeCo」で堅実な資産形成を
NISAとiDeCoは、それぞれ異なる特徴を持つ資産形成制度です。
- NISA:自由に引き出せるため、中期的な資金準備に最適
- iDeCo:資金拘束はあるものの、節税メリットが大きく老後資金を効率的に準備できる
iDeCoは「不人気」と言われがちですが、制度を理解して活用すれば非常に強力な武器になります。特にNISAと組み合わせれば、ライフステージに応じて必要なお金を効率的に準備でき、将来への安心感も高まります。
まずは自分のライフプランを見直し、余裕があればNISAに加えてiDeCoも検討してみてはいかがでしょうか。
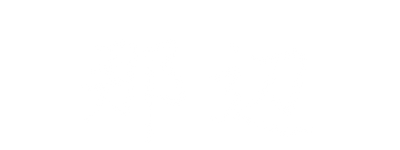
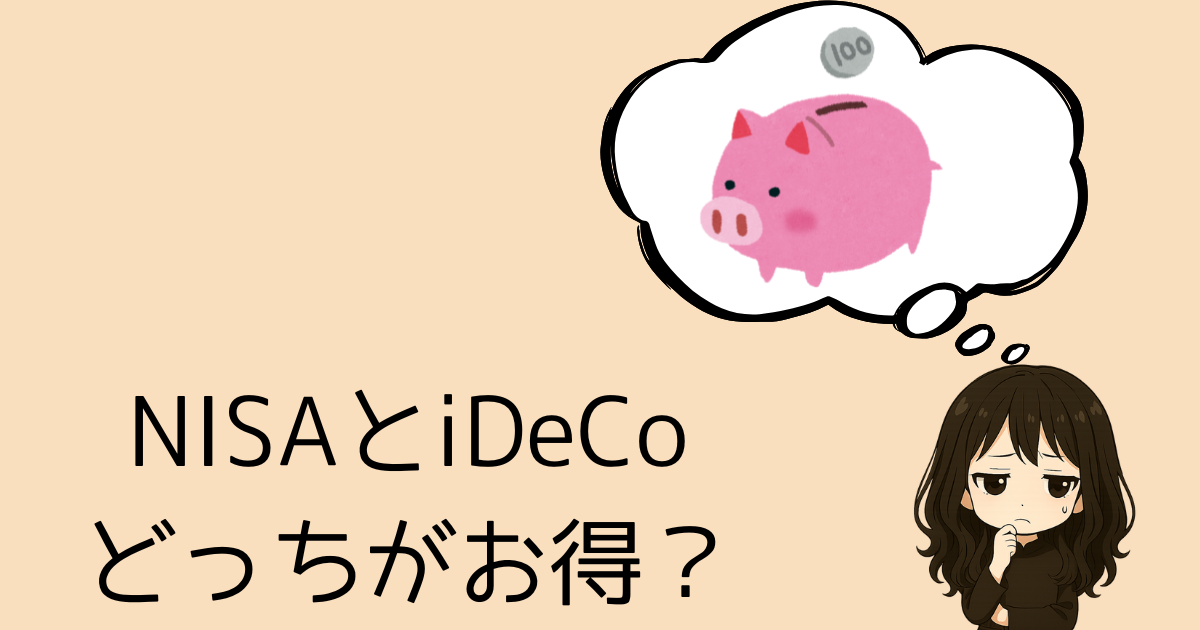
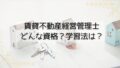

コメント