そもそも「情報技術者」というのがわからない。さらに「応用」らしい。わからない。謎すぎる。
そんなよくわからない資格ですが、なぜか受験しようと思い、幸運にも合格しました。
受験しようと思ったきっかけですが、業務で使っているシステムのリプレイスが必要になり、移行担当にさせられそうだったからです。
結果として、学んだ知識は移行業務にも役立ったのですが、それ以上にシステムを使ったり業務を管理するうえでのメリットを大きく感じました。現代はパソコンとかITなしで仕事ができる状態ではないので、技術者じゃなくても学ぶことに大きな価値がある資格だと思います。
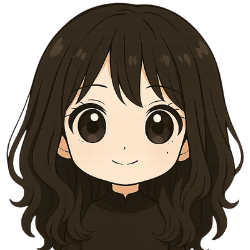
ちなみに文系、IT未経験(事務職)でしたがなんとかなりました。
そもそも応用情報技術者とは?
一言でいうと「ワンランク上のITエンジニア」らしいです。
IPA(情報処理推進機構)は様々な情報系の国家資格(試験?)を実施しています。対象と難易度からいくつかの種類に分けられており、対象は「ITを使う人」と「情報処理技術者」に、難易度はレベル1(易しい)からレベル4(難しい)になっています。
応用情報技術者はこのうち、「情報処理技術者」を対象にしたレベル3の試験です。
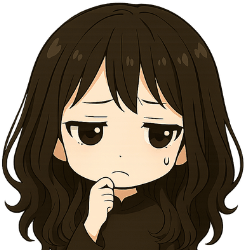
「情報処理技術者」…え?これ発注者側じゃなくて受注者側が対象なのでは?
ほんまや…
応用情報技術者はこんな人(IPA)
1.対象者像
ITを活用したサービス、製品、システム及びソフトウェアを作る人材に必要な応用的知識・技能をもち、高度IT人材としての方向性を確立した者
2.業務と役割
独力で次のいずれかの役割を果たす。
- 組織及び社会の課題に対する、ITを活用した戦略の立案、システムの企画・要件定義を行う。
- システムの設計・開発、汎用製品の最適組合せ(インテグレーション)によって、利用者にとって価値の高いシステムを構築する。
- サービスの安定的な運用を実現する。
応用情報技術者試験 | 試験情報 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 より引用
なんか、すごく凄そうな感じですね。
応用情報技術者はこんな人(私の考え)
まず、そんなつよつよエンジニアではないと思います。いや、もちろんつよつよエンジニアが応用情報技術者(AP)を取得すればつよつよエンジニアなのですが、それはAPのおかげではなく元からつよつよだっただけです。
そう考える理由として、まず試験そのものの構成があげられます。
試験は択一の午前と記述の午後に分けられます。そのうち午後は11分野から5分野(うち1分野はセキュリティが必須)を選んで解くため、プログラミングの知識やアルゴリズムの考え方がよくわからなくても、これらを選択から外せば何とかなります。
これはAPがITの上流から下流までを幅広く対象にした試験として設計されているからだと思います。ですので、AP=つよつよエンジニアではなく、IT全般に関してある程度の知識があるという方が実態に近いと思います。
受験者層としても、特定分野のエンジニアとしてバリバリやっていた方が他分野の知識を身に着けたり、マネジメント的な視点を養うための試験で、未経験が興味半分で受けることはあまり想定されていないような気がします。
とはいえ、未経験でもAP程度の知識があれば発注者としてベンダーとスムーズにやり取りすることができると思いますので、そういう点では未経験者が取得しても意味のある資格だと考えます。
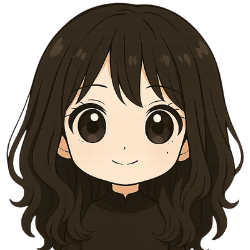
要するに、未経験者にとっては役立つ資格ではあるものの、APとってIT業界に転職できるかというと全くそんなことはないな、という印象です。
未経験でもAPは役に立つ
非IT業界で会社からAPが評価されることはまずないと思います。しかし、業務を行う上でAPの知識は非常に有益です。
具体的には、様々なシステムの挙動が推測できるようになるため、エラー時の対応や、システム間の連携をスムーズに行うためにどうすればいいのかがなんとなくわかります。
イメージですが、関数が読めるとエクセルを使いこなせるようになることに似ていると思います。
エクセルの関数が全く読めないと、既存のシートをメンテナンスすることができません。
関数が読めても、if文を無限にネストするようなレベルだと、可読性が死んでやっぱりメンテナンスが難しくなりますし、ミスにも気づきづらくなります。
やりたいことを整理して、入出力データを整理して、必要があれば中間データを作成することで読みやすく、わかりやすいエクセルシートが作れるのではないでしょうか。
同じようなことが業務システムにも言え、ローコードやノーコードのツールが出てきたことでその重要性は高まっているのではないかと感じます。
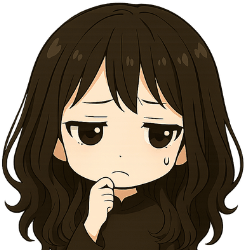
プロが開発したシステムならある程度の品質は担保されると思いますが、ユーザーが作るシステムは本当に質のばらつきが大きくなってしまうので、やばいシステムが業務に組み込まれてしまうと…時限爆弾ですよね。
なお、非IT業界でAP取得を公言することは全くお勧めしません。会社から評価されないのに、なんかパソコンに詳しい人みたいに思われてOA機器のトラブル対応とかを頼まれます。ひどいときには違う部署からも話が飛んできます。
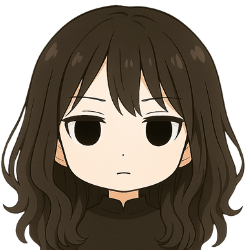
情シスに言ってください。というか、ドライバとかの設定ならともかく、ハードのことなんて全然わからないんだよなあ…
仕事と全然関係ないことでは、YouTubeの「IT業界あるあるネタ」なんかがちょっとだけわかるようになりました。プロマネコさんの動画とか、楽しく拝見させていただいています。
勉強法
午前試験はキタミ式テキストが非常にわかりやすかったです。
午後試験は重点対策本を購入したのですが、11分野のうち実際に受験するのは5分野、セキュリティを除いて考えると、必要になるのは10分野中4分野です。1分野予備を設けたとしても半分が必要ないということになってしまうので、正直過去問道場さんでもいいかな、と思いました(解説はもちろん、重点対策本の方が丁寧でしたが)
試験が記述なので、自己採点をしづらいという問題はありますが、気合で頑張りましょう。
【まとめ】社会人にはオススメ
というわけで、非IT業界の方でも社会人なら取得して損はない資格だと思います。
ただ、単にシステムを使うだけの人や、Officeの利用が大半という場合はオーバースペック気味かもしれません。それでも、ローコードやノーコードツール、生成AIの台頭などで非IT人材に求められるリテラシーのレベルも上がっているように思います。
ITに関する知識を網羅的、体系的に学習するという意味では非常に良い試験だと思いますので、ITの利活用に課題を感じている方は受験を検討されてみてはいかがでしょうか。
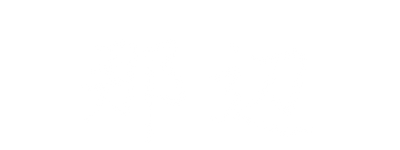


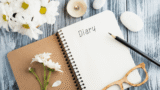
コメント