皆さんは「最速FIREのパラドックス」という言葉をご存じでしょうか。そんな方いらっしゃらないと思います。今私が考えましたので。
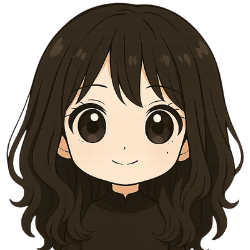
念のため、FIREとは皆さんご存じの「Financial Independence Retire Early」のことです。資産をためて、早期退職して、資産所得で生活しようというやつですね。
要するに、最速FIREを目指すと最速FIREできないというしごく当たり前の話なのですが、子育てしながら資産形成を続けていると実感をもってそのように感じるようになりました。
教育費で資産が減るから、とかいう話ではなく、そもそもFIREはFI(Financial Independence=経済的自立)とRE(Retire Early=早期退職)に分けて考えるべきだよな、という当たり前の話です。私みたいに仕事があんまり好きじゃなくてREしたいからFI目指すという人が陥りがちなのかもしれません。
FIREをFIとREに分けて考えるべき理由と、なぜ子育てしながらの資産形成でそのように感じたのかを整理してみました。
初めに自己紹介
地方都市、正社員共働き、2人の子どもを育てながら、資産形成も頑張ってます。今の仕事があまり楽しくないし、仕事人間という感じでもないのでさっさと退職したいなあと毎秒考えています。
転職も考えましたが、今の仕事は待遇自体は悪くないので子どもの手が離れるまでは今の仕事を続け、それから退職なり転職なりしようかな、と考えています。保育士とかいいな、と思って先日資格を取りました。ざっくりそんな感じです。
資産・生活状況
世帯金融資産が5,000万円弱、住宅ローンがあるのでそれを考慮するとアッパーマス層で、今の住宅が近隣相場で売却できれば準富裕層です。
夫婦の新NISAまでは何とか最短で埋められそうですが、その後は子どもも大きくなるので教育費でたぶん力尽きると思います。現在の貯蓄率は40%台なので資産を取り崩すことにはならないと思いますが、新NISA最短で埋めてしまうと現金比率が一桁%とかになりそう。そんな現金比率で大丈夫か?
マインド
FIREしたい勢です。コミュ障なので、社会の片隅で誰の気にも留められずひっそりと生きていきたいと思っています。
家計改善や資産運用を続けてきたおかげで、お金に関する知識もある程度実感を伴って持っていると思います。具体的には夫もFIREしたい勢なのですが、私がさっさとFIREするために夫には末永く働いてもらおうと思っています。
え?お金に関する知識ではない?
そうかもしれませんが、夫婦でFIREを考えたときに避けて通れないのが保険料です。特に国民年金は収入によらず賦課されるので退職後は負担がのしかかる(もちろん収入状況によっては減免などがある)のですが、なんと、2025年9月現在では配偶者の社会保険の扶養に入れば国民年金も健康保険も実質負担0なんです(早口)。
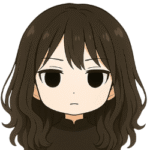
国民年金の第3号被保険者は今後どうなるかわかりませんが。日本は氷河期世代に対して何かうらみでもあるのでしょうか…
最速FIREを目指すと、最速FIREできない
FIREをFIREとしてとらえると、最速FIREをするためにはリスクを増やさざるを得ないため、結果として大きく資産を減らしてしまうことにつながりません。
自己資本(自分のビジネス)でFIREを目指す場合はちょっと違うと思いますが、私を含めた大半の方のように他人資本(株式や債券などのリスク資産)で資産を増やそうとする場合、最速で資産を増やすということは不可能です。
変に焦ってリスクを取りすぎると、焦りが逆効果となり、かえって資産を減らしてしまいます。
FIREには「FI(Financial Independence)」と「RE(Retire Early)」の2段階がある
私のように「仕事辞めたいな、よし、FIREだ!」と思うと、入り口の段階でFIとREがセットになってしまいます。
資産形成を始めたころはそう思っていましたが、資産形成を進めるうちに、実際にはFIを実現したうえで、どのタイミングでRE(サイドFIREのように労働強度を落とすことを含む)するかということを考えるべきだと感じるようになりました。
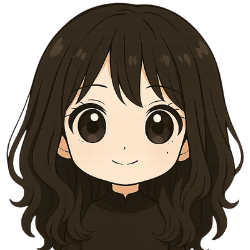
一刻も早く退職したい!だと退職という行為に自由意志が介在するためFIREを自分でコントロールできるよう錯覚していましたが、その前提となるFIは自由意志でどうにかなるかというと…ならないですよね。という当たり前の気づきです。
リスクを取りすぎると資産を減らし、むしろFIが遠のく
一般に、投資におけるリスクとリターンは表裏一体で、高いリターンを求めるならば高いリスクを受け入れなければなりません。ですので、最速でFIを実現するとなると、極めてリスクの高い運用をすることになります。
このリスクについては、投資商品そのものとアセットアロケーションの2つのリスクがあります。
投資商品そのもののリスクとは、値動きのボラティリティのことで、債権より株の方がリスクが高い、広く分散されたインデックスファンドより個別株の方が高い、といった感じです。
アセットアロケーションのリスクは、資産のうちどの程度をリスク資産(主に株式)に投資し、どの程度を安全資産(主に高格付けの債券や預金)に投資するかといった感じです。
前者については上を見ればきりがないですし、FIREを目指す多くの方はインデックスファンドを資産形成の中心に据えていると思います。ですので、この記事でいうリスクは後者の意味だと考えてください。
FIに到達する時期は相場次第で、自分ではコントロールできない
そしてインデックス投資を資産形成の中心に据えている多くの方は、
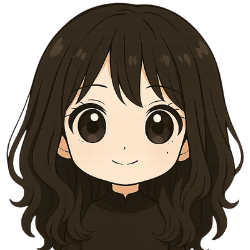
短期・個別の株の値動きはわからないけれど、長期・全体的な視点で見れば上がり下がりはあるものの、経済も株価も成長している。短期の最大リターンではなく、期待値を重視しよう。
という認識の元でインデックスファンドを選択していると思います。前提として短期の株価の変動はわからないことを受け入れているわけです。
そういうわけで、「最速でFIしたい」と思うのは、この前提と矛盾するな、と思うわけです。
相場が読めるのであればFIREの悩みなんて、一瞬で解決しちゃいますよね。
そういうわけで、最速FIについては「期待値を優先してリスク許容度の範囲内で可能な限りリスク資産を購入していたらいつの間にか達成していた」という結果論にしかならないと思います。
【妄想】REを実行するときに考えること
私はまだREできていないので、ここからは妄想です。
仮に、子どもが独立した、FIも達成した、となると、ようやくREを考えることになります。ですが、資産形成を続けてきた中で定期収入の価値を再認識するに至りました。
当たり前ですが、FIを達成したからと言ってすぐにREをする必要はないわけです。むしろ、REするまではREが人生の選択肢の一つですが、REした瞬間からもう退職前には戻れません。
給与収入を資産価値に置き換えて考えると、そのインパクトのすごさがお分かりいただけると思います。
月10万円の給与収入は1,800万円の価値がある
毎月10万円の給与収入と聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか。税金などを無視してざっくり計算してみます。
時給1,000円で月100時間、1月4週とすると1週25時間なので、週3日フルタイム勤務、あるいは週5で5時間労働くらいのイメージです。時給的にもバイトくらいの気楽さですね。
バイトして毎月10万円の給与と思うとたいしたことないように思えるかもしれませんが、FIRE目指す民からするとこの10万円は1,800万円の価値があります。
FIREする際によく言われる4%ルール(資産の取り崩しが年間4%なら資産が枯渇しない)で考えると、10万円×12か月÷4%=1,800万円だからです。このように、定期収入には実はものすごい資産価値があります。これが正社員で月収が20万円、30万円なら資産価値も3,600万円、5,400万円です。
だんだん労働が辛くなくなる
これは完全にメンタル的な話なのですが、同じ仕事を続けていても、資産が増えると精神的なストレスはどんどん減っていきます。
お金がなければ必死に会社にしがみつかなければいけません。給与が下がると生活できないからです。でも、資産があれば最悪首になってもバイトでもして、足りない生活費は資産収入から賄えばいいという気持ちになります。
たぶん、この選択肢があるということが重要で、人間にとって最もストレスなことの一つが選択肢がないことなんじゃないかなと思います。
ですので、REを目指してFIする時点で人生の選択肢が増え、労働がそれまでよりも苦ではなくなってきました。REはまだもうそうですが、これについては身をもって実感しています。
まとまった資産を安全資産に組み替える
REとなるとこれから使うフェーズに入ります。その時になんとかショックで株価が半値とかだと困るので、一般的にはREするならポートフォリオの安全資産の割合を増やすべきだといわれています。
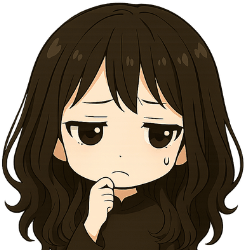
NISAで生債権は買えないし、投資信託もあまりいいものがない…安全資産は何がいいのかな?
いいですね。REに向けてそんなこと悩んでみたいです。
ですが、最近になってREはおろかFIするまえにこの悩みに真剣に向き合わなくなければなりました。
それが教育費です。FIの途中でありながら、近い将来使うことが確定しているため半ば強制的に安全資産で備えることが求められます。
FIの段階で直面する例外
FIは本来、ひたすら積み上げることに集中できるはずです。ところが実際には、子どもの教育費などの大きな出費が、このタイミングで重なることが多いです。
つまり「まだFIを達成していないのに、REのように資産を取り崩さざるを得ない」状況が起きるのです。
これは計画どおりに進めにくい厄介なポイントであり、ある意味では本格的なREよりも難易度が高い場面といえるでしょう。
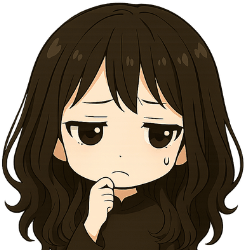
早く取り崩せば機会損失が生まれ、取り崩しを引き延ばすと取り崩し気に暴落に巻き込まれるかもしれない。REであれば暴落が来たら先延ばしすればいいだけなんですが、学費はそうもいきません。時期が決まった支出への備えは難しいですね。
FIとREを同時にこなすような難しさ
はじめにお伝えした通り、FIとREは異なる概念であり、本来であればFI→REという流れがあると思います。ですが、教育費のことを考えると、FIの最中に部分的にREをするようなリスク管理が必要となります。資産を増やす戦略と、減らさない工夫を同時に求められるため、バランスをとるのが難しくなるのです。
某有名マッチョライオンも「中期のお金を準備するのが一番難しい!」と言っていたとかいないとか。
我が家は今のところ教育費相当の蓄えについてもすべてリスク資産で運用していますが、子供が成長するにしたがって「そろそろ安全資産の割合の見直しが必要なのかな」とも感じています。
実際、初めから教育費を安全資産で運用していたらまだマス層だったと思いますので、今のところこの選択は結果論的に正しかったわけです。しかし、これからもそれが続くかはわかりません。
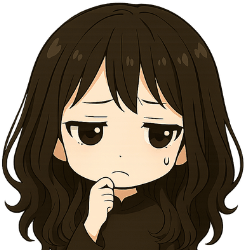
教育費には奨学金や教育ローンなどもありますが、一部の制度は資産形成を頑張ると所得や資産要件で対象から外れるのが辛いところです。
【まとめ】最速よりも安心してFIREできる形を目指そう
最速FIREを目指すあまりリスクを取りすぎると、かえって達成が遅れることがあります。
FIREはFI(経済的自立)とRE(早期退職)に分けて考えることで、無理なく資産形成を進めることができ、結果として人生の幸福感が上がるのではないかと思います。
また、教育費などのFI期の支出を軽視せず、借り入れを検討したり、安定資産で備えるなどの対策安心したFIREへの近道だと思います。
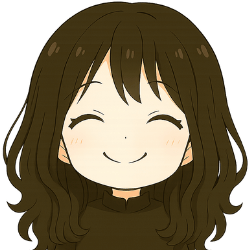
子どもの教育費のことを考えながら、アセットアロケーションを悩んでいるときに感じたことを私なりにまとめてみました。同じような悩みをお持ちの方の参考になれば嬉しいです。
ちなみに我が家は5年でNISAを埋めた後、子どもの大学受験まで少し時間があるので、追加投資をストップして現金比率を高めようと思っています。とりあえず上の子はそれで何とかなりそうです。でも高校から私立とかだと…どうしようかなあ。
大学も、国立なのか私立なのか、自宅から通うのか一人暮らしなのかで必要な費用も全然違うから本当に悩ましいですよね。
そうなると結局最大値で貯蓄することになるので経済は回らないし(資産)所得は増えなくなっちゃいますね…
あれ、北欧の公立大学が無償なのって実は福祉政策ではなくある意味経済政策なのでは?
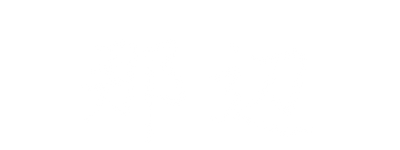




コメント