皆さんは「簿記」にどんなイメージをお持ちでしょうか。
就職や転職、スキルアップに向けた自己啓発によくお勧めされる簿記ですが、事務職や経理職の方(これらを目指している方)にはもちろん、すべての社会人の方におススメしたい資格です。
ビジネスシーンはもちろん、日常の家計管理や投資判断にも応用できる「お金の見方」が身につきます。資産形成にも役立つこと間違いなしです。
本記事では、簿記の概要とメリットを解説するとともに、実生活でどのように役立つのかをわかりやすく紹介します。
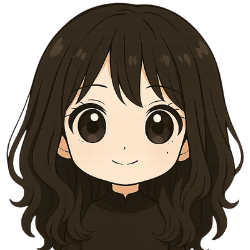
簿記とFPは全社会人が学ぶべき一般教養といっても過言ではないと思います。特に資産形成に興味をお持ちの方には特におすすめです。
簿記ってなに?
簿記を一言でいうと「収支と資産をわかりやすく管理するための会計の共通言語」です。もっとかみ砕いでいうと「企業の家計簿を作るためのルール」です。このルールに従って作られるのが決算書であり、これは企業の経営成績表です。
そういうわけで、簿記の技術としては企業会計のために必要なものですが、家計管理にも応用ができますし、投資(特に個別株投資)をする場合に決算書が読めるといろいろ役に立ちます。
私が考える簿記の大きな特徴は以下の2点です。
- 複式簿記(取引を2つの側面から記録する)
- 発生主義(取引の原因となる事実が生じた時点で取引が起こったものとする)
この2つは簿記の特徴であり、メリットであると思いますが、同時に初めての方にとっては感覚的に理解がしづらい点だと思います。以下、順番にご説明します。
複式簿記ってなに?
複式簿記とは取引を2つの側面から記録することです。
お金なんて増えるか減るかの2択だろいい加減にしろ!と思ったそこのあなた。
確かに家計簿ならそれでも悪くないのですが、例えば100円でお菓子を買った場合と投資信託を買った場合を比べてみましょう。
お菓子の方は食べたら終わりで財布から100円がなくなるだけですが、投資信託は財布から100円が減る代わりに投資信託という別の資産が100円増えます。
資産にだけ注目すると、前者は100円マイナス、後者は100円のマイナスと100円のプラスで差し引き0ということになります。
もう一つ例です。銀行から1万円を借りたとします。財布には1万円が増えますが、これを1万円の収入があった!と思う人はあまりいないと思います。財布に1万円の資産が増えた一方で、銀行に対して1万円の借金(負債)ができたので、資産の状況としては差し引き0だからです。
ちなみに簿記では資産から負債を引いたものを純資産といい、これがマイナスとなる(資産より負債が大きい)のがいわゆる債務超過です。
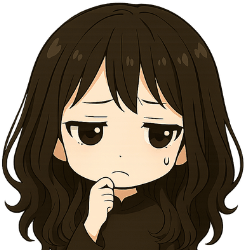
え?いやそんなの当たり前ですよね?
そう、簿記って別に難しい考え方とかルールがあるわけじゃなくて、実は当たり前で簡単なことなんです。お金を使った時に、消費して終わり(=費用が増えた)なのか、別の資産に形を変えた(=資産が増えた)のか、あるいは借金を返済した(=負債が減った)のか、これらをわかりやすく記録しているだけなんです。
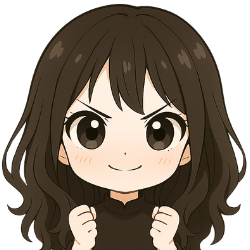
あ、でも最初の例には1つ間違いがありますよ。お菓子を100円で買った場合、確かに財布から100円はなくなりますが、100円分のやる気と幸せが得られます!
ごめんなさい、そういう定性的なものは簿記では扱わないんです…
発生主義ってなに?
発生主義とは、取引の事実が発生したタイミングで取引を記録するということです。
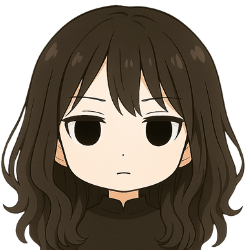
えーと・・・日本語が不自由な方ですか?
具体例で考えてみましょう。
Q1.アルさんが100万円でアパレルショップを始めました。1年目に50万円で仕入れた洋服が2年目に100万円で売れました。1年目と2年目の利益はそれぞれいくらでしょうか?
Q2.アルさんが10万円で2年間使える原付を買ってフードデリバリーを始めました。毎年1万円のガソリン代と、8万円の配達収入がありました。1年目と2年目の利益はそれぞれいくらでしょうか?

簿記的な正解はQ1が「1年目0円、2年目50万円」でQ2が「1年目も2年目も2万円」です。
Q1について、確かに1年目に50万円分の商品を仕入れていますが、これは50万円のお金(資産)が減り、50万円分の商品(資産)に姿を買えただけです。一方で、2年目は100万円の売上(収入)があり、100万円の現金(資産)が増え、50万円の商品(資産)が減りました。この50万円の商品の減少は、100万円の売上に必要な経費と考えられるので、50万円の費用が発生したと考えます。

収入に対応する費用は、その収入が発生した時に発生したと考えます。
Q2について、1年目に10万円(資産)が減り、10万円の原付(資産)が増えました。しかし、この原付は2年間使えるし、2年間しか使えません。2年で10万円の原付(資産)の価値がなくなるので、1年で5万円の原付の価値がなくなると考えます。ということで、1年目の利益も2年目の利益も8万円(配達収入)ー5万円(原付の価値減少分)ー1万円(ガソリン代)で2万円となります。

このように、事業に使う資産の価値を耐用年数に応じて減らす考え方を「減価償却」といい、簿記の重要な考え方の一つです。(なお、ここではわかりやすくするために残存簿価は0としています)
簿記の種類について
実は簿記には3種類あります。
最も受験者数が多く、就職や転職で評価されるのが 「日商簿記(日本商工会議所)」 です。就職や転職で簿記といえば、一般的にはこの日商簿記を指すことが多いでしょう。資格取得にしろ、スキルアップにしろ、これを選べば間違いありません。
そのほか、高校生を対象とした 「全商簿記(全国商業高等学校協会)」 や、社会人や学生が受験できる 「全経簿記(全国経理教育協会)」 もあります。
また、日商簿記には1級から3級まであります。
3級は初学者向けで、基本的な内容です。基本的な内容ではありますが、その基本がわかるとわからないの差が大きいと思いますので、転職に活かしたいなどの特別な事情がなければ、ほとんどの方にとっては3級で十分だと思います。
2級は実務者向けで、商業簿記だけでなく、工業簿記(原価計算)などが含まれます。業務で会計に携わるのであれば、持っていて損はないでしょう。私がもっているのも2級で、実際に中小企業で経理事務の経験がありますが、特に不自由は感じませんでした(申告業務は税理士にお願いしていました)。
1級はもっていないのでよくわからないのですが、大企業の経理などに役に立つらしいです。

簿記を学びたい方は3級、転職も視野に入れている方や、3級で簿記の魅力に気づいた方は2級、スペシャリストを目指したい方は1級という感じでしょうか。
簿記の資格を取る(簿記を学ぶ)メリット
ビジネス面では就職や転職への優位性があります。日商簿記2級以上は会計事務所、税理士事務所の求人条件でも歓迎資格(簿記2級程度の~という記載など)として挙げられるケースが多い印象です。
プライベートでは家計管理や資産運用、マニアックな使い方としては保育園や老人ホームの選択に役に立つこともあります。
決算書が読めるようになる
決算書は企業の経営成績表です。1年間の収支を表す「損益計算書」と決算時点の資産と負債状況を表す「貸借対照表」があります。この2つを組み合わせることで企業の経営実態が浮かび上がってきます。
「よくわからないけど、黒字を出して、増やしているのが優良企業なんだから、損益計算書だけあればいいんじゃないの?貸借対照表って必要?」
と思われたそこのあなた、そんなあなたに知っていただきたいのが「黒字倒産」という悲しい四字熟語です。
企業が倒産するのはいつでしょうか。赤字を出したときでしょうか?債務超過になったときでしょうか?
答えは「お金を払えなくなった時(そして、その支払いを待ってもらえなくなった時)」です。
では、どうして黒字なのにお金が足りなくなるかというと、黒字であることと現金が増えることが同じ意味ではないからです。
一番わかりやすいのが借金の返済です。借金の返済は損益計算書には出てきません。なので、利益より借金の返済が多い場合、その分のお金をどこからか持ってくる必要があります。
この原資は減価償却費(損益計算書には費用として計上されるけど、実際にお金の支払いが発生しない)だったり今までにためたお金だったりするわけです。減価償却費は損益計算書からわかりますが、今までにためたお金がどれだけあるかは貸借対照表を見なければわかりません。
このように、決算書を読むときは損益計算書と貸借対照表を合わせて見る必要性があるのです。
家計管理に活かせる
家計管理といえば家計簿ですね。家計簿をつけるときは、なんにいくら使っているかを把握して、どの支出を減らせるか、どれだけお金を残せるかを考えるのではないでしょうか。ですが、複式簿記の考え方では現金が減るときは、以下の3つのどれかが同時に発生しています。
- 費用が増えた(食費、日用品費、交際費などに支払った)
- 資産が増えた(有価証券、家、車などを購入した)
- 負債が減った(借金を返済した)
家計管理はどうしても「支出を抑制する」という考え方になりがちですが、本当は純資産を増やす視点が必要だと思います。この視点に立つと、資産の増加や負債の減少は純資産に影響を与えないため、家計に対して中立的な支出であると考えられます。
また、同じ資産(車)を買う場合でも
- タダでもらえて、5年間乗れるけど維持費が年間20万円、さらに処分費用がかかる車
- 5年後に100万円で売却できる200万円の車
では、後者の方が資産価値が高いことがわかります。
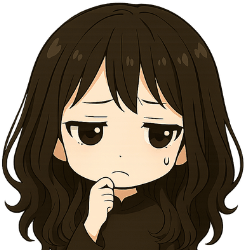
でも、後者の車はぶつけたらダメージがでかいですよね。前者の車は乗りつぶす前提なのでこすり放題、汚し放題なので前者の方がいいのでは?
その考え方も大いにあります。簿記が提供できるのはあくまで金銭的な視点だけです。例えば、前者の車が自分の好きな車でどうしても乗りたい、多少は高くお金を出していいと思っているのであれば、その選択も尊重されるべきでしょう。
資産運用に活かせる
決算書が読めるということは、当然資産運用にも活かせますよね。
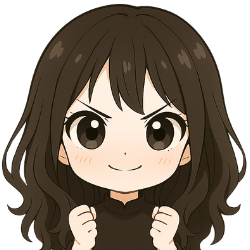
私も2022年から2023年にかけて、配当狙いで個別株投資をやっていました。その時はめちゃめちゃ決算書を読みまくっていましたよ!PER、PBR、自己資本比率、EPS、FCF、配当性向…
新NISAが始まってから枠を埋めるために売っちゃいましたが、その間は満足いくリターンが得られました。ほとんど市況が良かったおかげ威張れることではありませんが。
なお、新NISAになってからはインデックスに統一したので今では決算書は読んでいません。期待値の問題もありますが、個別株はやはり損益通算ができてほしいので。
保育園・老人ホーム選びに活かせる
決算書を読める、と同じことですが、これらのサービスを提供している社会福祉法人は決算書の公表が義務付けられています。
詳しくはこちらの記事でご紹介しています。
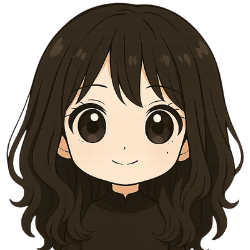
特に老人ホームは長い間お世話になる可能性もあるので、経営の安定性はチェックしたいところですね。
大人の嗜みとして、ぜひどうぞ
お金って仕事でもプライベートでも身近なことなので、簿記を学び、会計の基礎を学ぶことで、企業のお金の流れを理解できるだけでなく、自分の家計管理や投資判断にも応用できます。
また、3級は難易度も高くなく、通信講座や書籍も充実しています。独学でも挑戦しやすく、受験者も多いため学習環境が整っているのも魅力です。はじめて資格取得に挑戦する方にとっても、スムーズに取り組みやすいでしょう。
資格としてキャリアアップに活かすこともでき、知識として日常生活に役立てることもできる簿記。大人の嗜みとして、自己啓発の第一歩としていかがでしょうか。
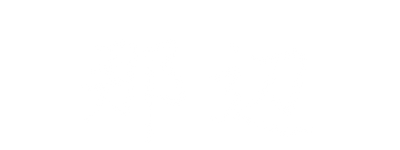
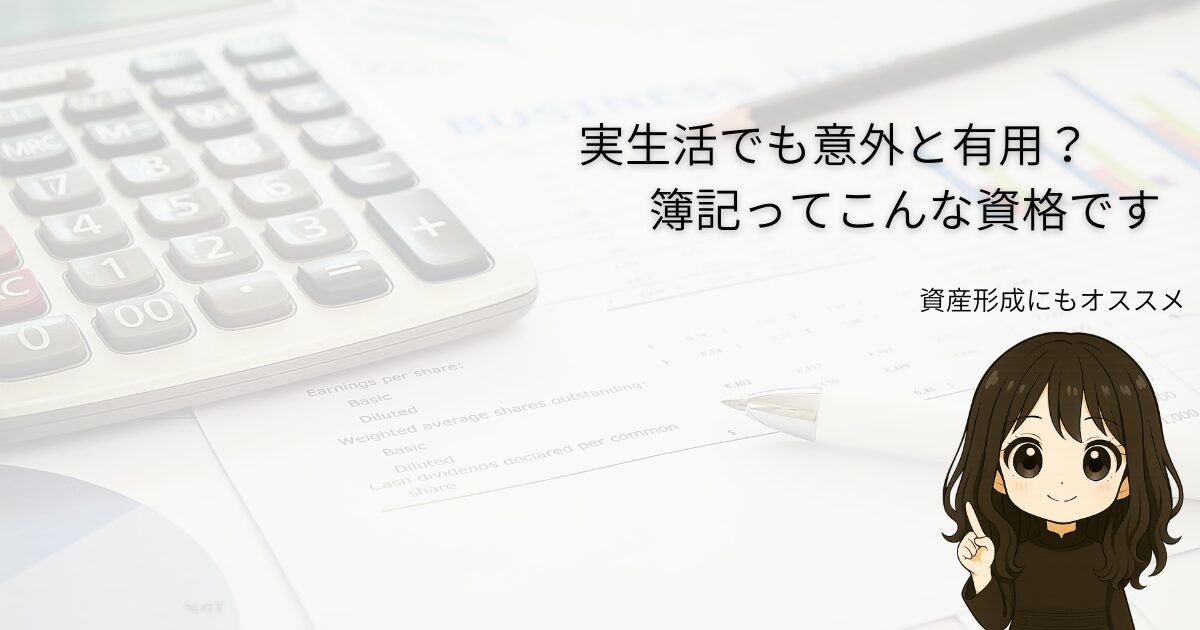



コメント