お盆休みに、久しぶりに市役所で働いている地元の友人と会いました。
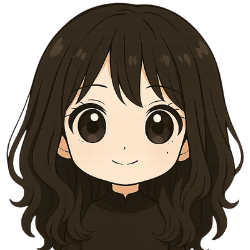
子どもが独立したら早期退職して、保育士として週数日働く生活を考えてるんだよね。いい保育園の見分け方ってあるかな?
と、私の近況を報告したところ、保育園選びの一助となる興味深い話が聞けましたので皆さんにも共有させていただきます。
保育園を選ぶとき、「家から近い」「園庭が広い」「雰囲気が良さそう」など、目に見える条件を重視するかたは多いと思います。
これらの条件ももちろん大切です。求職者なら面接を通じて、利用者なら施設見学などを通じてその園が自分に合うかどうかを判断することになると思います。
ですが、もうひとつ参考になるのが保育園の決算書(正しくは「計算書類」というそうですが、わかりやすいようにこの記事では「決算書」で統一します)です。多くの保育園は社会福祉法人により経営されていますが、社会福祉法人は経営状況の公開が義務づけられているそうです。つまり、決算書から収支のバランスや、支出の割合から園の方針・安定性を読み取ることができます。
もちろん数字だけですべてがわかるわけではありませんが、求職者にとっては「働きやすさ」、保護者にとっては「安心して預けられるか」の一つの判断材料になるかと思います。
この記事では、決算書から見える保育園のリアルと、最終的に確認すべきポイントを紹介します。

決算書はあくまで判断の補助材料にはなりますが、こういう視点もあるんだ、ということで。目次を用意していますので、気になるところからご覧ください。
保育園選びで大切な「経営の安定性」
保育園を選ぶとき、「園舎がきれい」「家から近い」といった条件に目が向きがちですが、見落とされやすいのが経営の安定性です。園を運営する法人の収支が不安定だと、その影響は職員や利用者にも及びます。
待遇改善が進みにくい構造的な背景もあるため、「長く安心して働ける・預けられる園かどうか」を見極める視点が欠かせません。
給与や待遇は大きく改善されにくい現実
保育士は「エッセンシャルワーカー」として社会に欠かせない存在ですが、給与や待遇が急激に改善される可能性は残念ながら低いそうです。というのも、保育サービスは福祉制度の一環としてその大部分が税金で賄われており、園の収入は公定価格によりほぼ固定化されています。つまり、園が自主的に「稼げる仕組み」を作るのが極めて困難です。売上があげられないのであれば、給料もなかなか上げられないですよね…
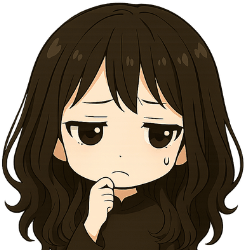
役所としては人件費としていくら、と計算して保育園にお金を渡し、その額は年々増えてはいるそうですが…人件費として使われている額(収入に占める割合)には大きなばらつきがあるのが現状だそうです。
そのため、「給与が高い園に転職したい」と思っても、他業種のように大幅な待遇差を期待するのは難しいとのことでした。保育士として働く上では、給与水準よりも園の安定性や職員同士の協力体制、保育内容の充実度に目を向けることが重要になります。
経営が不安定な園では職員や利用者にしわ寄せが来る
経営が不安定な園では、その負担が職員や利用者に跳ね返ってきます。たとえば、十分な人件費を確保できないために慢性的な人手不足に陥り、一人あたりの業務負担が増えるケースがあります。職員が疲弊すると離職も進み、結果的に子どもへの保育の質が低下してしまいます。
また、施設や保育材料(折り紙や色鉛筆など)への投資が後回しになり、子どもにとって安全で快適な環境が十分に整わないこともあります。利用者にとっても「安心して預けられるか」に直結する問題です。
だからこそ、園を選ぶ際には「雰囲気の良さ」だけでなく、経営の安定性を確認する視点を持つことも必要なのです。
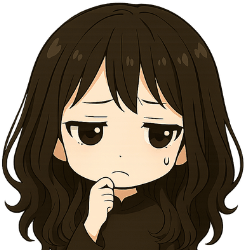
具体的なしわ寄せの例として、保育士の入れ替わりが激しいと乳幼児の愛着形成に必要な「特定の大人との応答的な関わり」が実現できません。また、新しいおもちゃや遊具がいつまでも導入されないといったこともあるようです。
社会福祉法人が運営する保育園は決算書を公開している
「経営の安定性を知りたい」と思っても、外からはなかなか見えにくいものです。
しかし、社会福祉法人が運営する保育園には大きな特徴があります。計算書類(決算書)などの経営情報の公開が義務づけられているため、誰でもインターネットで確認ができるのです。

「計算書類」が正しい表現のようですが、この記事では皆さんにわかりやすいように「決算書」で表現を統一します。
なお、決算書を読むには多少の簿記の知識が必要です。簿記というと難しいというイメージを持たれることもありますが、公私にわたりとても役に立つ資格です。スキルアップや自己啓発にもとてもおススメです。以下の記事で簿記がどんなものか、学ぶことでどんなメリットがあるかを紹介しています。
WAMネットで誰でも閲覧可能
WAMネットとは介護・福祉・医療などの制度解説や研修セミナー情報など、福祉・保健・医療の情報を総合的に提供している情報サイトです。
社会福祉法人には様々な情報公開があり、その一つに決算書の公開があります。多くの社会福祉法人がWAMネットの情報開示システムを利用して決算書を公開しています。
利用者や求職者も無料で閲覧できるため、園の経営状況を数字で把握することが可能です。普段は意識されにくい情報ですが、園選びの一つの判断材料として活用できます。

社会福祉法人が対象なので、介護サービスや障害サービスに関する情報もこちらから確認できます。
公開の背景にある「透明性」の確保
社会福祉法人が行う事業は(老人サービスなど一部利用者負担が主となるものもありますが)主に公費により運営されています。また、税制面でも様々な優遇措置があることから、一般企業以上に「経営の透明性を公開すること」が求められています。
決算書の公開は、法人の信頼性を高め、地域社会や保護者に対して透明性を示すための仕組みです。つまり、数字を確認することは「園がどのような姿勢で保育事業を行っているか」を知る手がかりにもなるのです。
これに関連して印象的だったのは、友人が言っていた「利用者も適切なサービスを選ばなければならない」という言葉です。
皆様の中には社会福祉法人と聞いて、あまりいいイメージをお持ちでない方もいらっしゃるかと思います。実際、社会福祉法人が内部留保をため込みすぎだとか、経営が杜撰だということが社会的な問題になったため、このような透明性の確保について様々な対応が求められるようになったとのことです。
彼女曰く「そのような経緯があって、たくさんの情報が公開されているのだから、利用者が適切にサービスを選択することを通じて社会福祉法人に対して健全な経営がなされるよう働きかけなければならない」とのことでした。要するに、利用者が質の低いサービスを選ばないことでダメな施設を淘汰したり、利用者に選ばれるようサービスの質の向上に努めてもらうべきだということです。
私も保護者として保育園を利用したことがありますし、保育士試験にも合格しましたが、WAMネットのことは彼女に聞くまで全く知りませんでした。反省です…。
もちろん、現実には選べるだけの選択肢がないケースもあると思います。子どもを預けるに足るいい保育園がないからと言って、いつまでも仕事を休むことはできないでしょう。しかし、サービスの利用者もサービスを構成する一員であることから、適正なサービス運営に対する責任があるのだな、と考えさせられました。
決算書から見える保育園のリアル
決算書なんて難しそう…と思う方も多いでしょう。ですが、ポイントを絞って見るだけでも園の特徴が見えてきます。特に注目したいのは収支の安定性、人件費の割合、施設や保育材料への投資です。これらは働きやすさや子どもが過ごす環境に直結しています。
収支のバランス(赤字が続いていないか)
まず確認したいのは「収支のバランス」です。赤字が一時的なものなら問題ありませんが、数年連続して赤字が続いている場合は注意が必要です。経営が不安定だと、職員の雇用や子どもに提供されるサービスに影響が出る可能性があります。

WAMネットではかなりさかのぼって決算書を見れます。収支は基本的に事業活動計算書(中身は損益計算書とほとんど同じ)でわかりますが、貸借対照表の純資産を見ると過去の利益の蓄積が一目でわかります。
人件費の割合(職員への還元度合い)
決算書では人件費の割合も見るべきポイントになります。保育は人が中心のサービスなので、人件費は大きな割合を占めるのが自然です。極端に低い場合は職員に十分還元されていない可能性があり、逆に高すぎる場合は経営の余裕がなく将来の投資に回せていないかもしれません。バランスを見極める視点が大切です。
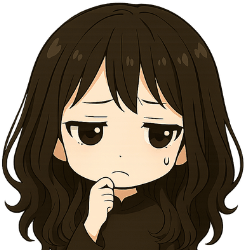
人件費率が高いからといっていい園とは限りません。きちんと利益が出ているかも大切ですし、人件費はあくまで総額です。後述しますが、人件費が一部の人間に偏っているケースもあるようです。
なお、事業活動計算書では職員給料(いわゆる正職員の給料)、非常勤職員給料、派遣職員費と雇用形態ごとの人件費の割合も分かります(賞与については雇用形態ごとの区別なく、職員賞与として計上されるそうです)
なお、保育士確保に苦慮する園の一部は人材紹介サービスを利用しており、手数料に高額な支出が計上されている場合に該当するケースが多いそうです。もちろん、手数料のすべてがサービス利用料というわけでもないでしょうし、サービスの利用が悪いわけではありませんが…

ご存じの方も多いかと思いますが、保育士1人が見ることのできる園児の数には決まりがあります。保育士が突然やめると、預かっている園児を見るのに十分な保育士がいないということになり、至急保育士を確保する必要が生じます
施設や保育材料への投資状況
子どもが安心して過ごすためには、安全な施設や保育教材が欠かせません。
施設については建物の築年数によって支出の状況が大きく異なるため一概に判断することは難しいです。こちらについては実際に見学する方が決算書より有益かもしれません。
それでも、貸借対照表の器具備品(遊具などはここに分類されることが多いそうです)の残高などからわかる情報はあります。
保育材料については、事業活動計算書に「保育材料費」という項目があり、こちらから確認することができます。

「職員被服費」「研修研究費」なども、保育士として働くうえでは待遇の参考になる費目かもしれません。
決算書だけではわからないこと
決算書は客観的な資料ですが、数字だけですべてを判断できるわけではありません。会計処理の方法や法人の体質によっても見え方は変わります。過信せず、あくまで「参考資料のひとつ」として捉えることが大切です。
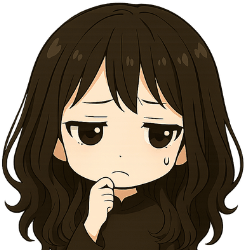
残念ながら事務が苦手な社会福祉法人もあるそうで、中にはとても独創的な仕訳で決算書を作っているところも…あるとかないとか
一族経営など、数字には出ない実情もある
社会福祉法人では、一族経営の法人も少なくありません。法人役員になれる一族の数には制限があるそうですが、職員として運営に携わるケースもあり、決算書で人件費の割合が高かったとしても、もらっているのは一族ばかり、ということもあるようです。
(一族経営に関する注意点は保育園に限ったことではありませんのでここでは深く取り上げません)
あくまで「参考程度」にとどめる姿勢が大切
数字はあくまで「園の全体像の一部」を切り取ったものにすぎません。「経営が黒字だから安心」「赤字だから危険」「人件費が高ければいい」などと、単純に判断することはできませんし、決算書だけではわからないこともたくさんあります。

極端な例ですが、少子化が進む中、将来的に閉園を決めているのであれば、それに向かって過去の利益を取り崩す形で赤字が継続したとしても問題があるとは言えません。特に、赤字が減価償却の範囲内であれば基本的には資金繰りにも問題は生じないです。
経営の安定性はもちろん大切ですが、最終的には、現場を見て判断する姿勢が欠かせません。実際に現場を訪れたり、働くのであれば面接の場で、預けるのであれば見学などを通じて総合的に判断することで、良い選択につながると思います。
【まとめ】決算書+現場の両面から、安心できる園を選ぼう
保育園を選ぶとき、決算書は「経営の安定性」を知るための有効な材料です。ただし、それだけに頼るのではなく、実際の現場や人間関係、保育方針を確認して総合的に判断することが大切だと思います。
数字を見る力を身につけたい方には、簿記の学習もおすすめです。ビジネスだけでなく家計管理にも役立つ実用的なスキルであり、園選びにも応用できます(簿記紹介の記事も近日中にUP予定です)
【余談】私の体験談
保育士として働いたことはありませんが、利用者として子供を預けたことはあります。その際は周りの先輩から評判を聞いたり、実際に見学に行ったりして、園を選びました。当然、当時はWAMネットのことなどは知りません。
見学では園によって雰囲気がかなり違っていたと驚いたことを覚えています。すごく塩対応をされた園もありました。
当時はまだ待機児童が全国的な問題になっていた時代で「受け入れてもらえるだけマシ」という風潮も強かったのですが、なんとか保活を頑張った結果、子どもも毎日楽しそうに通ってくれる、満足のいく園選びができたと思っています。
印象的なことの一つが、園長先生が子どもたちからすごく慕われていたことです。おそらく、園長先生が保育の現場に直接かかわることはそう多くないのではないかと思います。なので、園長先生が慕われているということは、園長先生、ひいては保育園がしっかり子どもたちに向き合ってくれているということじゃないかな、と思います。とすると、これは何気にいい保育園の条件の一つかもしれません。いや、N=1なので信ぴょう性は全く自身ないですけど。
記事を書くにあたり、今更ですがお世話になった園の決算書を見てみました。経営は安定しつつも利益をため込みすぎているわけではなく、園児や職員に適度に還元されているように感じました。もともと利用していて間違いないことはわかっているのですが、今、保育士として働くなら、ぜひその園で働きたいと思っています。
皆さんもWAMネットを使って、利用者としてのリテラシー、高めてみませんか?
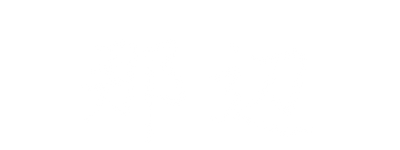


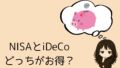

コメント