「賃貸不動産経営管理士」という資格をご存じでしょうか?
2021年に国家資格となった比較的新しい資格で、従来の不動産三冠資格(宅建士、管理業務主任者、マンション管理士)とあわせて不動産四冠資格と呼ばれることもあるようです。
私自身も2024年に管理業務主任者と同時に独学でこの資格を取得しましたが、その過程で感じたこと、工夫した勉強法などを本記事でまとめました。
「どんな資格?宅建との違いは?」「どうやって勉強するの?」といった疑問をお持ちの方の参考になれば幸いです。
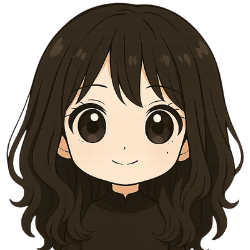
資格紹介シリーズ第1回目!目次を用意していますので、気になるところからご覧ください
賃貸不動産経営管理士とは?
賃貸不動産経営管理士がどんな資格なのか、国家資格になった背景、他の不動産系資格との違いなどについて、ご紹介します
どんな資格?
賃貸不動産経営管理士は、賃貸不動産の管理業務の専門家です。物件のオーナーに代わって物件の管理や、入居者対応を行います。具体的には物件の修繕対応や、退去時の原状回復などです。賃貸物件における「管理会社」のお仕事ですね。

分譲マンションにおける「管理会社」とは別物です。後程ご説明する不動産資格の比較表でご確認ください。
ほかにも、民泊やサブリース(転貸借)関連の業務についても対応することがあります。
残念ながら、現時点で独占業務はありません。必置義務はあり、一定以上の規模の管理業務を行う場合、営業所に業務管理者を配置する必要があります。賃貸不動産経営管理士はこの業務管理者の要件の一つではあるのですが、2025年7月時点では一定の要件を満たした宅建士も業務管理者となれるため、「もう全部宅建士一人でいいんじゃないかな」といわれているとかいないとか
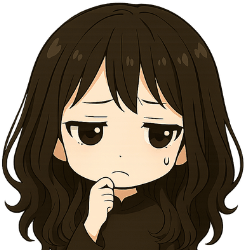
宅建士であれば入居者の募集業務も行えますもんね・・・
国家資格となった背景には、オーナーと入居者のトラブル防止とか、人口減少に伴い空き家が増えるのでその管理を適正に行う必要があるとか、サブリースで問題が起きまくったとか色々あるようです。
資格の詳しい説明は、試験実施団体である賃貸不動産経営管理士協議会のホームページからご確認いただけます。
宅建・管理業務主任者・マンション管理士との違い
不動産系資格には似た名称のものが多く、「どれがどう違うの?」と迷う方も多いと思います。ここでは代表的な3資格と比較してみます。
| 資格名 | 主な対象 | 業務の中心 | 必置義務 | 独占業務 |
| 宅建士 | 売買・賃貸の仲介 | 契約時の重要事項説明など | あり | あり |
| 賃貸不動産経営管理士 | 賃貸住宅の管理 | 物件管理、入居者対応など | あり | なし |
| 管理業務主任者 | 分譲マンションの管理 (管理会社側) | 分譲住宅の管理業務など | あり | あり |
| マンション管理士 | 分譲マンションの管理 (管理組合側) | 管理組合のコンサル業務など | なし | なし |
ちょっと乱暴ですが、分譲マンションで管理業務主任者が行っている業務を賃貸物件に対して行うのが賃貸不動産経営管理士といえるかもしれません。
表だけだとわかりにくいかもしれませんが、賃貸不動産経営管理士は賃貸契約の募集・仲介を行うことはできません(宅建士の業務になります)
なんで受験したの?
ここまでのご説明で勘のいい方ならお気づきでしょう。そう、「あれ、もう全部宅建士でいいんじゃない?」と。
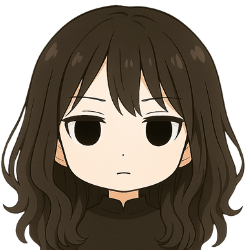
・・・あなたのような勘の良い方は嫌いです
私が受験した理由は以下の3つです
- 国家資格化に伴い、今後難化するかもしれないと思ったから
- 宅建士が業務を担えるのは経過措置で、今後は賃貸管理業務は賃貸不動産経営管理士だけになるかもしれないし、もしかしたら重要事項説明も独占業務になるかもしれないと思ったから(※)
- 同時受験する予定のマンション管理士、管理業務主任者と内容が結構かぶっていたから
はい、めちゃめちゃ打算的ですね。1と2はともかく、3に関しては結果として大正解でした。
試験の概要と難易度
試験は全50問、四肢択一で、合格点は年によって変動します(相対評価方式)
主な出題範囲は民法、賃貸住宅管理業法、設備管理などです
今のところ、不動産四冠資格では一番簡単といわれていますが、国家資格になってから日が浅いせいか、出題範囲や形式についての変動が大きいという印象を受けました。
試験内容について
2025年7月時点での試験出題範囲は以下の通りです
- イ 管理受託契約に関する事項
- ロ 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項
- ハ 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
- ニ 賃貸住宅の賃貸借に関する事項
- ホ 法に関する事項
- へ イからホまでに掲げるもののほか、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項
※問題中の法令等に関する部分は、令和7年4月1日現在で施行されている規定(関係機関による関連告示、通達等を含む。)に基づいて出題します。
賃貸不動産経営管理士協議会HPより引用
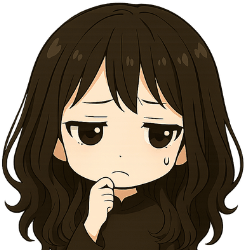
範囲が示されているようで示されていないような気がしますね。ホの「法」って何のことでしょうか・・・
私の勉強法
- マンション管理士の勉強を頑張る
- 試験の1か月くらい前にテキストを一通り読む
- 過去問をひたすら解く
賃貸不動産経営管理士としての勉強時間は多分20時間くらいだったと思います。民法や設備関係についてはマンション管理士の受験内容を押さえていれば追加での学習は不要だと思います(原状回復については償却年数など一部追加で学習するポイントあり)
また、賃貸住宅管理業法についてはマンション管理士試験と内容がかぶっていないので、こちらも追加でインプットが必要です。
過去問は過去問道場さんでの学習がオススメです。解説もしっかりしてます。出題形式や難易度が大きく変わっていたためどこまで過去問をやるかは迷いましたが、出題数が50問になった令和2年以降の問題を周回しました。
なお、私が受験した令和6年度は合格点が35点でしたが、自己採点では38点でした。ただ、FPや資産運用の知識があったから解けた問題もあったような気もします。
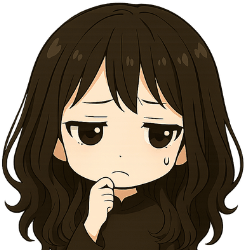
保育士試験もそうなのですが、出題範囲が広いとどうしても問題との相性が出てしまいます。賃貸不動産経営管理士は相対評価なので、出来ない問題はみんなも出来てない、と思って割り切りしかないです。
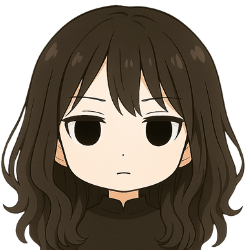
余談ですが、マンション管理士は不合格でした。
受験した感想
相変わらず仕事には何の役にも立っていないのですが、原状回復ガイドラインの考え方などは、自分が入居者になる場合でも役に立つな、と思いました。
制度の内容がこれからも変わらないのであれば「宅建士でいいじゃん」という結論は変わりませんが、今後どうなるかわかりませんし、合格に有効期限もないので、管理業務主任者やマンション管理士を受験予定の方は同時受験を検討してみる価値は十分あると思います。
おまけ:5問免除は必要?
所定の講習を受けると、2年の間、5問免除が受けられます。私は講習を受けなかったのですが、令和6年の試験結果を見ると講習の有無で合格率に有意な差が生じています(賃貸不動産経営管理士協議会のHPで統計データが公表されています)
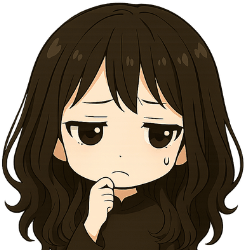
令和6年の全体合格率は5問免除なしの方で20.6%、5問免除ありの方で29.7%とのことです。宅建のように講習受講に現職である必要がないため公平といえば公平なのですが、講習の有無で合格率が1.5倍近くも違うというのはそれはそれでどうなのかな、という気もします。もちろん、講習を受ける方のほうがモチベーションが高いと思われますので、同一条件で比較ができるとも思っていないのですが…。
個人的には、5問免除はなくてもいいかな、と思います。理由としては
- 5問免除がなくても合格率は20%程度はあり、必須というほどの難易度でもない(5問免除がなくても宅建程度の合格率はある)
- 他の不動産系の5問免除と違い、どの分野が5問免除になるかわからない(学習しなくてよい分野が作れるわけではない)
からです。とはいえ、事実として令和6年は受講の有無で合格率に大きな差が生じていますので、仕事で必要な場合など、どうしても合格したい理由があればこの限りではありません。ただ、資格試験にあまり課金要素が持ち込まれるのは…どうなんでしょうね。どうでもいいですが、合格の書類とあわせて実務講習を強めにプッシュする案内が入っていたりと、全体的に課金圧を感じる試験でした(個人の感想です)

資格エンジョイ勢の一意見、ということでご了承ください。
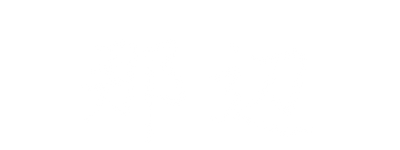
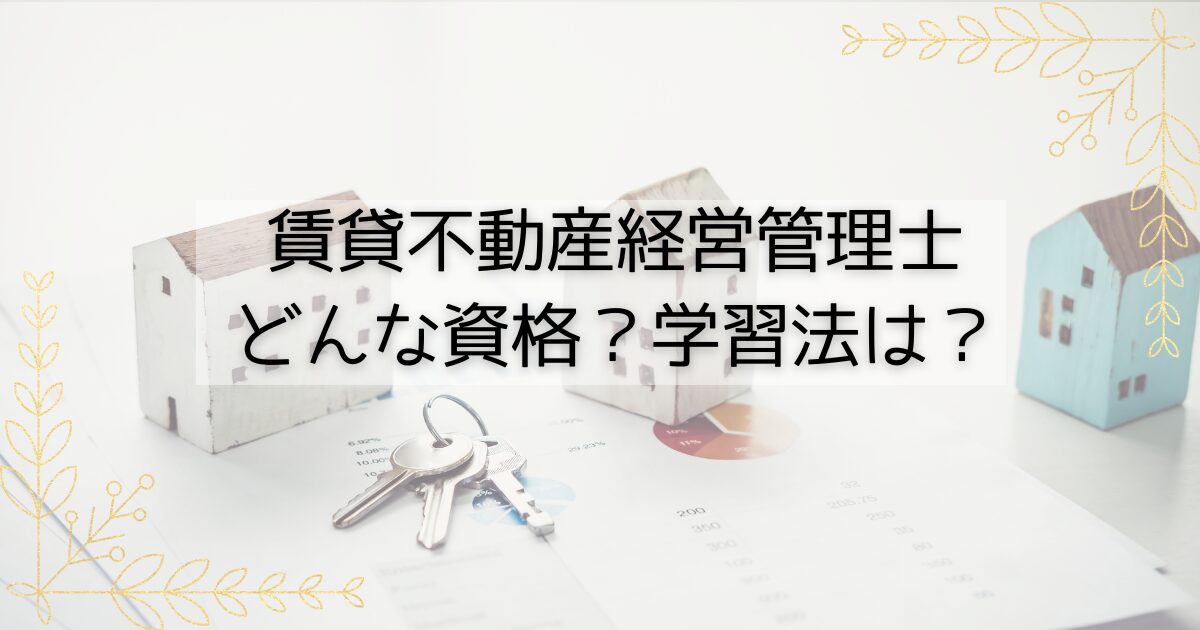

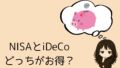
コメント