先日、令和7年前期の保育士試験合格発表があり、無事合格できました。
勉強の開始は1月中旬から、1日の勉強時間は平日1時間・土日2時間程度で、フルタイムで働きながらでも運よく1回の受験でなんとかなりました。
スケジュール、勉強法、試験当日の心構えなど、詳しくまとめてみましたのでこれから受験される方の参考になれば幸いです。
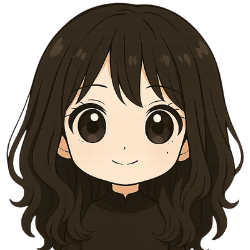
体験談なので、かなり主観が入っています。ご了承ください。
目次を用意していますので、興味のある項目からどうぞご覧ください
私の状況について
これから受験を考えている方のご参考まで、私の状況を簡単にご紹介します。受験について特段のアドバンテージといえるのは子育て経験があることと、ピアノをちょこっと弾けるくらいです。ピアノは受験に必須ではないので、多くの人に参考にしていただけるのではないかと思います。
生活スタイル
- フルタイム共働き
- 子どもは小学校高学年で、育児の負担はそこまでナシ
- 仕事は事務職なので、基本的な子育て経験はあるものの、未経験での受験です。免除科目もありません。
- 子供のころピアノをやっていたので、ピアノは多少弾けます
- 2024年から興味を持った資格に挑戦しており、基本的な勉強週間はありました
受験しようと思ったきっかけ
子どもが小学校高学年になり、休日も家族といるより友達と遊ぶ方が多くなりました。子育てについての手間は減りましたが、一抹の寂しさを感じることも。
そんな時、流し見しているYouTubeから流れてくる愛らしい赤ちゃんたちの癒され動画。かわいい。年の離れたご兄弟がいらっしゃるご家庭の気持ちが今ならよくわかります。しかし、現実的に我が家にその選択肢は取れない。年齢とか家の間取りとかお金のこととかあれとかこれとか。少子化とはこういうことか。そこで私は思いました。
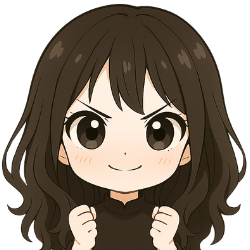
保育士になるしかない
真面目にお話ししますと、子どもが好きというのもですが、退職後の働き口としても意外とありなのでは?と思ったことも理由の一つです。
私は将来、早期退職したいと思っています。が、フルリタイアではなく、退職後も週3程度で働ければいいなと考えています。そうなったとき、資格があるとやはり有利かな、と思って頭が働くうちに・・・と受験に至った次第です。
保育士試験の全体像と難易度
簡単に保育士試験の全体像と、受験して感じた難易度のご紹介です。
保育士試験の全体像
保育士試験は筆記試験8科目(教育原理と社会的擁護は併せて1科目)、実技試験2科目(音楽・造形・言語から2つ選択)から構成され、いずれも6割以上の得点で合格となります(絶対評価方式)
実技試験に進むためには筆記試験を全科目合格する必要があります。筆記試験には科目合格制度があり、合格した科目については3年間免除が受けられます。
幼稚園教諭の資格があったり、大学で特定の単位を取得していると一部科目が免除になったりもするようですが、私には残念ながらそんなものありませんでした。
受験した感じ、科目ごとの出題内容に明確な線引きがあるわけではない気がしました。また、子どもに関する内容が中心ではありますが、社会福祉や保育の心理学など一部の科目では小学生以降どころか成人、中年、老年に関する内容も学びます。出題範囲は相当広いです。
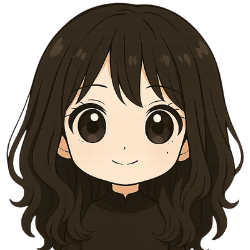
科目合格の制度があるため、人によっては複数回の受験を前提に受験計画を立てる方もいらっしゃるようです。詳しくは次の「難易度」のところでお話ししますが、個人的には受験計画としては1回合格を目指す(結果として複数回になることはある)方が良いかと思います
保育士試験の難易度
私の場合、トータルの勉強時間は大体150時間ぐらいでした。ただ、1発で合格できたのは正直運が良かったと思います。
筆記試験のところでも書きましたが、保育士試験は範囲がとにかく広いです。合格圏内まで知識を増やすのは割とスムーズにいきますが、確実に合格できるといえる水準まで知識を増やすのはなかなか現実的ではなく、問題との相性次第では複数回受験もやむなしかと思います。
実際、私も子ども家庭福祉については得点が60点だったので、1問間違っていれば不合格でした。過去問は過去10回分以上を反復して解き、どの回も9割以上は取れるようにしていたにも関わらず、です。
また、範囲が広いからこそ、科目同士の学習の相乗効果が見込めると思いました。例えば子ども家庭福祉と社会福祉は福祉制度の考え方が根っこでつながっているため、別々に学習するよりもまとめて学習したほうが効率が良いです。
ほかにも、保育所(保育原理)と幼稚園(教育原理)を対比して学習することで理解が深まるなどの効果もありました。
この辺は人によるのかと思いますが、学習が大変だからと初めから複数回受験前提で捨て科目を作ってしまうと、かえって合格までに必要な勉強時間が伸びてしまうように感じました。複数の科目が関係しあっているからこそ、まとめて勉強することが効率的だと感じました。
一生懸命勉強しても、問題との相性次第では残念な結果になることもありうる試験だと思います。ネットで言われるほど簡単な資格ではないな、と感じました。
科目合格の有効期間が3年とやや長めになっているのは、保育士を増やしたいという思惑のほかに、範囲が広いことに対する受験者への救済措置の側面もあるのかもしれません。
実際の勉強方法とスケジュールなど
勉強方法、やったこと、使った教材、スケジュールなどなど、具体的にご紹介します。
勉強方法
テキストを読んで内容をまとめる→過去問を回す→再度テキストを読んで内容をまとめる→過去問を回す→不足している知識を足す
という方法で進めました。
択一式の資格試験については、いきなり過去問を解いた方がいいという人もいますが、私はまずテキストを読みます。
また、内容をノートにもまとめます。こちらについてもテキストに書き込んだ方がいいという方もいらっしゃいますね。私は学習後にテキストをフリマアプリで売るために書き込みをしませんでした学んだことをしっかりと自分の言葉でアウトプットするためにノートを作る派です
使用したテキストはこちら。1冊で全科目を網羅してくれるすごいやつです。問題集は購入せず、過去問は過去問.comさんにお世話になりました。
また、通勤時間やすき間時間にYouTubeを使ってインプットも行っていました。特にお世話になったのは四谷学院さんの保育所保育指針の聞き流し(Youtube)と、ほいくんの保育士チャンネルさん(Youtube)です。
スケジュールと勉強内容
1月中旬から筆記の勉強を開始しました。しかし、運悪く仕事で大きめのトラブルがあり、残業続きで平日はなかなか学習時間が確保できませんでした。それでも何とか土日は頑張り、2週間くらいでテキストを一通りまとめ終わりました。
2月から過去問に取り掛かりました。このころには仕事も落ち着いていたので、平日も1時間くらいは勉強時間を確保できていました。過去問.comさんではWeb上で年度や科目を指定して過去問を解くことができますので、こちらで科目ごとに過去問を解いていき、頻出テーマや苦手分野をなんとなく確認しました。スマホさえあれば過去問が解けるので、昼休みにも問題を解いていました。
2月中旬ごろに全科目の過去10回分が終わり、再度テキストのまとめを行いました。1回目のまとめとの違いは、過去問の出題傾向や自分の苦手分野を踏まえ、より自分にとって最適化されたものになるように心がけます。また、余白を少し多めにとり、後から追記できるスペースも作っておきます。
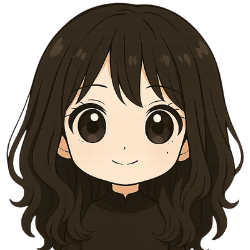
1回目のまとめはせず、いきなり過去問を解いた方が効率的かもしれませんが、何もわからない状態で過去問を解くと過去問から得られるものが少ない気がして、このスタイルに落ち着きました。
3月に入ったら、過去問の2週目に取り掛かります。間違えた問題や、消去法で正解した問題で過程を正しく理解できていなかった問題については内容をまとめノートの余白に書き込んでいきます。
また、併せて直前の詰め込み用の項目を整理していきます。保育士試験ではたくさんの単純暗記項目(人名や理論、栄養素の名前と働きなどなど)が出てきて、こればかりは詰め込むほかありません。ロジックがあるものについてはまとめノートで整理しながら記憶に定着させ、詰め込むものは直前に対策します。
試験日まで、過去問→まとめを繰り返します。苦手な分野はさらにさかのぼって過去問を解きました。ただ、法令の改正が多いものなどはあまり古い過去問を解きすぎると最新の内容と混乱することになるのでその点はご注意ください。
また、速く読んで、速く解けるように時間についても意識します。詳しくは試験当日の過ごし方でお話ししますが、出来るだけ早く途中退室し、勉強時間を確保するためです。
6月の筆記試験合格発表後、実技の対策に取り掛かりました。言語の台本はホイビィの保育士×未来ラボさん(Youtube)のものを参考に、音楽の楽譜はこぱんピアノさん(Youtube)のものを参考にさせていただきました。
年度が替わると課題も変わると思いますが、同じようにYouTubeなどで探していただくと参考になるものが見つかるかと思います。
言語については、以下の3点を意識して練習しました
- 台本を丸暗記するよりも、大まかな話の流れを覚えることを心がける(当日、セリフが飛んでもあせらずに済むように)
- 3つの課題それぞれ、大体の文字数が同じになるように調整する(課題が違っても話す速度が同じくらいなら、同じくらいの時間で終わるように)
- 身振りを入れる場所を決めておく
音楽については、メトロノームを使って練習し、テンポが一定になるように意識して練習しました。
試験当日の過ごし方
いよいよ試験本番です。保育士試験は筆記が終日2日と長丁場です。また、実技は試験時間こそ短いものの、人によってはかなり待機時間が長くなります。実際に受験して感じた、試験当日のお勧めの過ごし方を紹介します。
筆記試験
筆記試験のお勧めの過ごし方についてはこの一言に尽きます

ささっと問題を解いて、途中退室しましょう
試験時間は1科目1時間で、試験開始から30分経過すると途中退室ができます(教育原理と社会的擁護を除きます)
途中退室すると、試験終了後に答案を回収する時間なども次の科目の勉強に充てられます。科目間のインターバルは30分(お昼を挟む場合は1時間)ありますので、試験開始10分前に入室すると考えても、30分で退室できれば50分の時間を確保できます。
この時間を利用して、人名など直前に詰め込みが必要なものを詰め込みます。50分もあれば大抵のものはなんとかなります。また、関係する統計資料などもこのタイミングで確認することをオススメします。
なお、会場には試験室のほかに待合室が用意されており、途中退室した場合は待合室で勉強できます。
実技試験
実技試験は、朝の集合時間こそ決まっていますが、その後のスケジュールは人によりバラバラです。会場の受験者数にもよりますが、場合によっては2時間とか3時間とか待ち時間が出ることもあると思います。
会場では音を出しての練習ができないので、筆記の時のように何かをするというよりは、空いた時間をどう過ごすかをあらかじめ決めておくといいと思います。スマホの電源が切れないように、モバイルバッテリーを持っていきましょう。
当日の過ごし方とは少し異なりますが、実技試験について私が感じたことを紹介します。
まず、皆さん気になる服装ですがこれは本当にいろいろな方がいらっしゃいました。ジーンズの方もいらっしゃいました。私自身はオフィスカジュアルくらいの格好で行きました。
また、会場によっては持参品に「上履き」と記載があります。よくわからなかったのでわざわざ室内用の靴を買ったのですが、スリッパ(たためるルームシューズ的なものを含む)をもってきている方が多かったようです。ピアノでペダルを使わないなら、スリッパでいいと思います。受験票はよく読んでおきましょう。
実技に関しては筆記と違って客観的な採点基準があるわけではありませんが、一生懸命練習したことがきちんと伝われば合格にしてくれるような気がしました。
私自身が、上手ではないけどへたくそではない、一生懸命頑張りました、くらいの出来栄えで大体7割だったので。私自身の当日の様子を振り返るとこんな感じでした。
音楽については、明確に反省点がありました。それは伴奏をシンプルにするべきだったということです。特に「証城寺の狸囃子」ではセブンスコードが入っているのですが、弾き語りで4音弾くと伴奏が重くなりすぎると感じました。

これはシンプルに練習と本番の環境が違ったことが原因ですね。電子ピアノで練習している場合は陥りやすいと思います。可能であれば、アップライトピアノでリハーサルができればよいのですが・・・なかなか難しいですね。
「伴奏は単音でもいい」という意見を拝見しましたが、案外その通りかもしれません。電子ピアノで単音の伴奏だと何とも心細いですが、アップライトピアノだとそれでも十分形になるように思います。
そもそも、子どもが楽しく歌えることが目的(たぶん)だと思うので、伴奏が重厚かどうかとかはあまり関係ないようにも思います。
リハーサル以外での対策でいうと、最初のあいさつでできるだけ大きな声を出すということでしょうか。前述の通り、会場では音出しでの練習が禁止です。数時間ぶりにいきなり大きな声で歌うというのは厳しいと思いますので、入室時の「失礼します」や「よろしくお願いします」で気持ち大きな声を出しておくと、そのままの流れで弾き語りに入れるのではないかと思いました。
【まとめ】これから受験される方へ
実際に受験してみて感じたことをまとめました。
- 筆記試験はテキストと過去問を科目ごとに反復し、理解を深める
- 捨て科目は作らず、1回での合格を目指す
- けれども範囲が広い試験なので、問題との相性次第では1回で合格できない場合もある。こればかりは仕方ない。
- 音楽の伴奏はシンプルでOK
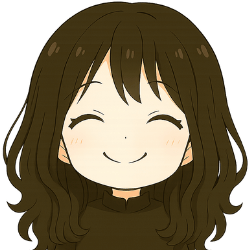
これから受験する方の参考になれば幸いです
【おまけ】資格取得にかかった費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 受験料 | 13,000円 | 決済手数料込 |
| テキスト代 | 3,740円 | |
| 交通費 | 3,600円 | 片道600円×2回×3日 |
| 上履き | 1,000円 | |
| 登録費用 | 5,000円 | 郵送料等含む せっかくなので登録します |
| 合計 | 26,340円 |
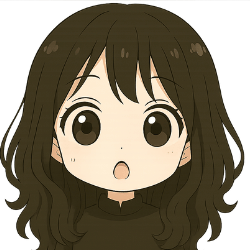
登録費用が約5,000円とは良心的ですね。合格だけして、登録費用が高すぎて登録していない資格がたくさんあります・・・名称独占資格ではありますが、更新もないし、せっかくなので登録しようと思います。
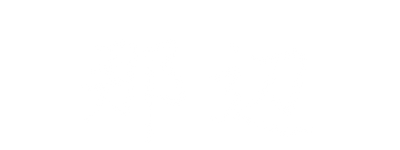


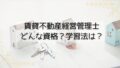
コメント